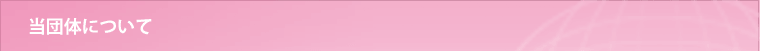

私は二十年目を歩み始めている。
更年期医療のけもの道のことである。
その時の私に明確な「女性外来」の認識はなかったけれど、私が名づけた「女性成人病クリニック」の名称から考えれば、意識的に男女性差を意図したことは確からしい。
これらのことを回顧しようというには既に記憶が曖昧すぎるし、といって懐古というのも世捨て人じみて悲しいし。
複雑な年齢になってしまった。
二十年前、私は循環器内科の勤務医であった。
その時点で私は既に三十年、そのなりわいで生きていた。
私は所帯持ちでもあり、子持ちでもあった。
日々の生活は多忙を極めていたが、若さで突っ走っていた日常に、ついに異変の影が射してきたのが五十過ぎ。
体中が痒い、乾く、冷える。落ち着かないこと甚だしい。
ひとの話が遠くに聴こえる。上昇中の飛行機内みたいに会話が外耳から中に入らない。
人前で突然言葉が出なくなる。物怖じしてる訳じゃないのにスピーチの途中で言葉を失い立ち尽くす。
とてつもない疲労感と無気力に苛まれる日々。
何時間寝ても取れない疲れに心が折れてしまう。旅行も映画も音楽も、もうどうでもよくなっていた。
そんな状態で二、三年が過ぎ、もう限界だ、もうこれ以上は無理だ。生来そんなに丈夫ではない私。ここまでやれたら上出来じゃないか。誰が褒めなくても私自身が褒めてやる。
そう考えて常勤医を辞したのが55歳。
それから一年ちょっとで私はホルモン補充療法に出会うことになる。自分が更年期障害に苦しんでいたとはっきり自己診断したからではない。その当時の私に、更年期という文字がちらついたことがあっただろうか?
皆無である。今では信じられないけど、皆無であった。
私は、当時流布されていた更年期神話の信者であった。
忙しく懸命に有意義に生きている女性は更年期障害みたいな、暇人の贅沢病には罹らない、という経典に基づく信仰である。
当時、その、信仰に似た思い込みは、医者であればいっそう強固なものになり得たのである。四、五十歳の女性たちの、あんな訳の分からないぐたぐたに、保険診療で縛られている我々はマジでは付き合えないのだという、暗黙の了解事項だったのかも知れない。
医者をしていて且つ「家政婦のミタ」状態の私だからこそ、その経典の精神論には強固に同意していたわけで、日常をこなせないほどの状態にありながら、自分が更年期障害のド壺にはまり込んでいるなんて夢想もしなかったし、更年期のコの字も頭をかすめることはなかった。
ホルモン補充療法との出会いは、日本のホルモン補充療法の第一人者小山嵩夫氏の文献が縁になった。閉経後の女性の高コレステロールは循環器科の常識であったが、それがエストロゲンで改善するとその論文には書いてあった。
数年前から私にもお定まりの高コレステロール血症が発症していたが、スタチン系薬剤が十分に効果を上げていた。
同僚の医者にも聞いてみたが、そんな治療法はやったことがないと。当然だ、私も寡聞にして知らない。
今更とは思ったけれど、エストロゲンが私の脂質代謝にどう働くのか実証してみたいという好奇心のほうがスタチン剤に勝った。
そこでそれまでの薬剤を中止し、コレステロール値がリバウンドしてきたことを確認後、エストロゲン(プレマリン)一錠を服用することにした。
私とエストロゲンとの出会いは、ここから始まった。
手のひらの一粒の白い錠剤を口に入れることにいささかの躊躇いがあったことは確かだ。自分で飲んだことは勿論、人に処方したこともない。ましてや女性ホルモンだ。なんだか隠微な響きを感じてしまう。同じホルモンでも、副腎皮質ホルモンや甲状腺ホルモンには感じないミステリアスな響き。
えい、やっ、と口に出したわけではないけれど、まあそんな感じと勢いでその錠剤は私に飲み込まれていったのである。
その一錠は、干上がった砂漠に水を灌ぐように私を潤していった。コレステロール値をチェックするよりもはるかに素早く、あのしつこい全身の痒みを消し、顔面の痛いほどの乾きを消し、気が付けば、瞬時も素足を許さなかった冷えを消し去ってくれていたのである。
私の心身は数年前に戻って行ったように感じた。まるでタイムカプセルを飲み込んだみたいだった、私の場合は。
心身の苦痛が瞬く間に消えていったその日、私は診療後の診察室で泣いた。
なぁんだ、私、更年期障害だったんだ。
五年間も、私、それに気づかなかった。退職した上、これが私の老後かと猫を抱いて陽だまりにうずくまり足の冷えを癒していた。
なぁんだ、たったこれ一錠で。
ただただ涙が溢れ出て、私は声を飲み込みながら泣いていた。
長い間、私は四、五十代の女性の患者さんを診るのは苦手だった。訴えていることの訳が分からない。頭も肩も腰も動悸も不眠も耳鳴りもめまいも何もかもをそんなに一度に訴えられたって!
でも、私はその日のうちに私は理解した。
私のところで体中の不調を訴え続けていた大勢の女性は、気のせいでも暇人でも贅沢病でも過剰なストレスに負けたわけでもなかった。
彼女たちは本当に苦しかったのだ。
私は内科医としてそれが全く理解できなかった。
循環器内科医の私のところには、主に動悸や息切れを主訴にする女性が来院する。先ずは胸部レントゲン写真や心電図が手掛かりになる。心音や血圧や血液検査なども調べてみる。
心臓には別に悪いところはないですね、心配は要りませんと私は告げる。
あの頃、実は私もそうだった。何十年も上り下りしている駅の階段が異常に苦しい。途中で休んだり、上りきれば柱に寄りかかったまましばらくは動けない。なにが起きたのかと心電図を調べたり心エコー検査までやったが異常なし。
だからもう放っておいた。
でも、と彼女たちは続ける。不整脈も出ます。肩も痛いくらいに張ってきて頭痛もしてきます。まるで孫悟空のヘアバンドのような輪でぎゅうっと締め付られて。マッサージも温泉も、いいのはその時だけ。体を拭いているうちにまたぐう~っと張ってきます。
私には求められている答えが出てこない。
睡眠不足ではありませんかと訊いてみる。待ってましたとばかりに彼女らは口を開く。寝つきが悪いし眠りが浅いし、他で眠剤をもらっているのですが、いくら飲んでもよく寝たという気がしない。疲れも取れない。何もしたくない、台所に立つ気もしない。ちょっとした家族の言動にもイライラ腹が立って、夫婦喧嘩の絶え間がない、と。
ここまでのやり取りの間に、私のほうもかなりイライラしてくるが、もしも私が動悸から夫婦喧嘩まで、見事に医学的決着をつけたとしても、彼女たちは更に訴え続けるだろう。目が回るんですよね、耳鳴りもするし、手がしびれて、腰や膝も痛いのですが、と。
四、五十歳代の女性は、だから苦手なのであった。
私は循環器科の医者だ。肩こりや夫婦喧嘩の診察までは勘弁してほしい。
それに、あなたは私の机上にまだ何十人ものカルテが積み重なっているのを見てるでしょう。あなたは他の方の診察時間も使っているのです。そのことに気づいて下さいますか。
ごめんなさい。
ほんとは訳の分からない訴えではなかったのですね。更年期症状には、みんな意味があったのに。
その中の一つか二つだけのコンビネーションにしつこく付きまとわれるひともいれば、五つも六つもの症状に襲われて倒れこむ人もいる。
私の場合も複数の症状に五、六年もの長きにわたってつきまとわれた。このくらい長いと、もう元の自分がどうであったかなどは忘れてしまう。更年期症状に飼いならされ、不調の心身に自分を合わせ、縮小したサイズて生きていく術を身に着けてしまうのだ。
一錠の女性ホルモンで、私は長い間忘れていた、まともだった頃の自分にふっと戻っていた。悪夢から覚めたようなあんばいだった。
われを取り戻した私は、四、五十歳の訴えの多い女性たちの謎が、一瞬のうちに解けたと思った。まさに氷解である。
なんて私ってバカだったのだろうという苦い悔い。三十年余の間には何百人しかしたら千人を超えたかもしれない女性たちが、曖昧な結論に納得のいかぬまま診察室を出て行ったのだ。
彼女たちの失望と無念を思うと今でも暗然とした気分になる。
苦い悔いが私を責めた。三十年の医者としての在りようが情けなくて申し訳なくて恥かしかった。
そしてもちろん、この数年間に私個人が失ったものの取り返しのつかない大きさを思うと胸が痛む。
苦い悔悟の涙を流しながら、私はどこかで怒っていた。私が受けた医学の教育の中で、閉経期の女性の様々な訴えを、「エストロゲン」の視点から指導されたことはあっただろうか。産婦人科の医師すら更年期障害を積極的な医療の対象にしてはいなかったではないか。
この悔悟と怒りが引き金になり、私は、九か月後にはエストロゲンを使う更年期医療の専門外来を開くことになるのである。
しかし、我ながら思い切ったことをやったものだと私は思う。症例は私自身の一例だけ。
しかしこれには、私はもう絶対的な自信を持っていた。女性ホルモンは私の数年間の苦痛を、私の場合、ほとんど一瞬のうちに消し去ってくれた。
私のように見事に有効であった症例は、その後の経験でも正直なところそうはいなかった。私とはよほど相性が良かったらしい。
私には、数年前に私が持っていたエネルギーが甦っていた。57歳の私の背中を開業に向けて押し続けてくれていたのは、一日一粒服用していた女性ホルモン剤である。確信をもってそれは言える。
その頃調べていた昭和初期の文献で驚いたことが一つある。その時代に、既に更年期症状は研究しつくされているのである。ホットフラッシュという言葉はさすがに見られないが、ほてり、のぼせ、多汗という言葉が紙面に溢れている。
子宮や卵巣を摘出した女性のことを「宦官婦人」と記してあるのには驚いたけれど、そのような言葉を論文に用いていた時代から、更年期は大きな研究テーマであったということだ。
そして昭和三十年代、更年期障害にエストロゲンが著効であることは認めたものの、子宮がんの発症を報告する論文も散見されるようになり、エストロゲ単独使用のホルモン補充療法は終止符を打った。
二十年前、小山嵩夫氏は子宮がんの発症率を低下させるプロゲストン併用療法を日本に紹介する。
私が彼の書いたものに目が留まったのはその頃の話だ。その中のコレステロールの項目にだけ目が行ったのだけど。
「女性成人病クリニック」は、慌ただしくスタートした。
数か月間はほんとうに後悔した。私はとんでもないことを始めてしまったんじゃないか。いったい私に何ができるというのだろう、と。
三十年も循環器の医者をやっていた。今までなら胸部のレントゲン写真があり心電図があり聴診器があった。そこを拠りどころにして診断を広げていった。
今は何もない。あるのは聴診器と時間だけ。
心細く受診者の胸元に目が泳ぐ。習慣とは恐ろしいものだ。
やがて、彼女らは心臓を診てもらいに来たのではなく全身を診てもらいに来たのだと気が付いた。
そして始まった。肩が凝って頭は輪をかぶせたようにきりきりと痛くなります。顔は火照るのに足は氷のように冷えるのです。耳鳴りが続きます。めまいは治るでしょうか。異常に疲れます、大したことやってないのに。眠れません。
イライラします。このままだと私は夫を刺してしまうかもしれません。夫に触れられるとぞっとします、嫌いじゃないんだけど。
週半日、小山嵩夫先生のサポートをお願いしてあった。そのことを彼に訴えた。「そのうち、どこを掴むか、コツが分かってきますよ」。その通りだった。
話の内容は多岐に亘った。病状と関係のあるものも無いものも私は聴いた。
私は彼女たちから多くを学ばせていただき、多くの人生を教えられた。彼女たちは苦しみ、時に涙を流した。もらい泣きしたことも幾たびか。
こうして更年期との縁を深めて、早二十年経ってしまったという訳だ。
「恨はん」という言葉をご存じだろうか。
「恨」は日本語では遺恨の「恨こん」であって文字通り「恨み」の意味。これには
個人的な感情が先立っている。が、「恨はん」は朝鮮語で、恨みは恨みでも、ちょっと奥行きが異なる。
「恨」には、大韓民国の苦難と屈辱の歴史に根差した民族的な深い悲しみと怒りの感情が含まれている、と広辞苑には書いてある。
更年期に「恨」を持ち出すのはちょっと大袈裟だと思うかも知れないが、私が更年期外来を始めた二十年前は、私は本当に彼女たちに「恨」を感じた。「恨み」ではなく「恨」である。それは女族の国の苦難であったと思えるからだ。
女性の全員が不具合になるわけではないけれど、私のように望んだわけでもないのにパート勤務にならざるを得ないケースがある。男社会で必死に頑張ってきた女性が、誰にも理解されないまま退職した例がある。退職しないまでも、
昇進を諦めた例もある。家庭にあっても、不調のまま夫にも子供たちにも理解されずに孤立している女性も多かった。
彼女たちは「恨」の残渣を抱えて、今、老後を生きている。目指した生き方を理不尽に閉ざされた思いは、終生心のどこかに無念を生む。女族の「恨」である。
私が更年期外来を開業したのは1992年の12月である。
その頃、私はある座談会で、21世紀は医学書が書き換えられるだろうということを発言した。つまり、医学書の中に「中高年の女性に多発する」と言い放たれた文言は、ことごとく研究者によって解明実証される世紀だろうと言いたかったのである。
そこに天野惠子氏がいた。
彼女は思いつくや素早く研究をし行動をとった。
彼女の圧倒的な力によって、ついに、先ず循環器学が変わった。閉経期の女性の胸痛発作の研究である。新しい教科書には「微小血管狭心症」の項目がなくてはならない。
更に、彼女は医学部のカリキュラムにも関与し、多くの大学に教育から「性差医学」を認識させる努力をしている。私は更年期障害の教育について不満を述べたが、多分そこは当然変わることになるだろう。
この期間、私たち臨床医も頑張った。多くの女性誌が更年期特集を組んだが、声がかかれば積極的に取材を受け、誠実に答えてきた。
記者さんやライターさんも、最初はなかなか理解困難であったようだが、最近は更年期のことを正しく理解してくれていることが、取材されていてもよくかる。
この人たちが、女性誌だけでなく一般誌にも、更年期や更年期障害について詳しく易しく丁寧に書いてくれる。
ほとんど毎月のように、何かの雑誌が更年期を扱っている時期もあった。
そのおかげで、受診なさるかたも、更年期をよく理解しておられる。診察時の説明が楽になった。
そして、何よりも変わったのは、彼女たちに、ほとんど苦悩の影がない。つまり、「恨」の雰囲気がなくなったことだ。また、夫や家族も、更年期に対して
理解ある態度で接してくれているようだ。
彼女たちは、更年期症状の出る前から受診する。早手回しに検査を受けておこうという人も多い。
ひどくなって来るのはカッコ悪いからというのだ。
長寿の時代、元気な年寄りでいたいからとも。
こうなると、今や更年期医療は『「恨」の医学』ではなく『「希望」の医学』
そのものだ。
私のやっている更年期医療は、今では女性医学乃至は女性医療の一部門に過ぎない。
これからは、あらゆる診療科目に性差医学的視点が必要になってくる。
「女性外来」開設以来十年になるという。
しかし、まだ、婦人科と乳腺科があれば「女性外来」だと考えている医者がいる。
女医だけを集めれば「女性外来」が成立すると考えている医者もいる。
では、「女性外来」がそんなものではないことを説明できる医者がどのくらいいるだろう。
「女性外来」は、まだまだ進化途上だ。
どう変わっていくのか、見つめ続けたい。
村崎芙蓉子
(女性成人病クリニック)
Copyright © 2014 Japan NAHW Network. All Rights Reserved.