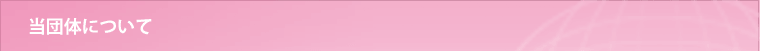
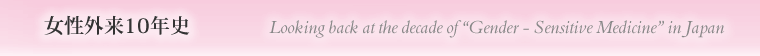
佐賀大学循環器内科河野宏明
社会の高齢化と生活習慣の変化に伴い、メタボリック症候群や動脈硬化性疾患が増加しており大きな社会問題となっている。日本での死因の1位は癌に代表される悪性腫瘍である。しかし、2位は脳血管障害、3位は心疾患である。動脈硬化、メタボリック症候群に関係する死因は2位と3位を占めている。平均寿命の変遷を見てみると、どの年代をとっても男性より女性の方が長生きである。最近では女性の平均寿命は87歳前後、男性は78歳前後である。これはなぜか?大きな疑問である。我が国は遺憾にも世界でもトップクラスの自殺が多い国である。社会はもっと働き盛りの人々に救いの手を差し伸べる必要がある。社会での生産性の高い人々を守る必要がある。早急に手を打たないといけない大きな問題である。自殺者は女性に比して男性の方が圧倒的に多い。ここにも性差が存在する。働き盛りの男性および女性が働きやすい社会を作ることが、少子化対策にも繋がるし、今後の日本の生産性の向上に繋がり、世界での地位向上にも大きく寄与するものと考える。税制や社会保障制度も含めて、国民皆で議論する必要がある。寿命の話にもどるが中高年での自殺者が多いから・・・・・?だから、女性の方が平均寿命が長い?しかし、心疾患の代表の一つである狭心症、急性心筋梗塞は男性では60台後半、女性では70台後半に発症のピークが来る。したがって、自殺者の性差のみが平均寿命に大きな影響を及ぼしているとは思えない。“人は血管とともに老いる“という言葉ある。原因の一つには、血管の老化の問題があるのかもしれない。女性は閉経後に動脈硬化性疾患に罹患やすいことが知られている。したがって、女性ホルモンが動脈硬化進展抑制に働いていることが推測される。実際、正確なメカニズムは不明であるが女性ホルモンの抗動脈硬化作用については少なからず報告がある。たぶん、女性が動脈硬化疾患になりにくい、平均寿命が長い、メタボリック症候群になりにくい、などの理由の一つに女性ホルモンの働きは少なからず影響していると思われる。しかし、これだけで全てが説明できるほど単純なものではない。
以前より疫学的に性差が存在する疾患は知られていたが、その理由はなんとなく曖昧にされて来た。基礎あるいは臨床研究も含めてオスまたは男性を中心にして行われてきており、その結果を基にして治療法や投薬量の決定がされてきた。確かに、男性と女性では体格も、生理現象も、社会的な役割も異なっている。したがって、性差を考慮した基礎あるいは臨床研究を行い、疾患のメカニズムや治療法について明らかにし、臨床に応用2していく必要がある。例えば、循環器の分野では女性は心電図異常が出やすい、QTが延長しやすい、運動負荷試験で偽陽性が多いなどの特徴がある。心筋内の微小循環が影響しているのかもしれないし、女性ホルモンが影響しているのかもしれない。未だに良くわからない。大きな冠動脈には異常は無いのに狭心症様症状が出現する、いわゆる微小血管狭心症も女性に多い。これも理由は分かっていない。医学の世界では病気の発症に大きな男女差をみる疾患が数多く存在する。高安病、膠原病、偏頭痛などは女性に多く、痛風などは男性に多い疾患の代表である。このような疾患の場合には男女差を考えて診療を行っているが、循環器疾患や神経疾患(認知症は女性に多い)のように男女に共通した疾患の診療を行う際にも、男女差について考えながら診断治療を行うことは必須のことである。しかし残念ながら、大学では男女差に気を配った診療を行うようなことは教育していない。ある意味、あたりまえのことが教育されていないのである。天野先生が提唱された性差医療の考え方はこれからの医療には必須の考え方である。女性外来は女性を対象とした外来を指すと考えられるが、なにも医師も女性である必要は無いと思われる。意外に男性の視点からしか分からない女性の疾患が見えることも少なくない。
現在の性差医療は女性医療に焦点が当てられている。これは更年期障害など女性特有の疾患を女性医師が相談にのってくれる点が人気を集めている理由の一つなのかもしれない。平均寿命の延長に伴い、余命と健康寿命との隔たりが生じ、障害のある期間が長くなるなどの問題が生じている。したがって、余命のみならず健康寿命を延長させる必要があると思われる。「女性専用外来」を設けることで、日ごろなかなか話しにくいことを医師に相談することができ、精神的疾患や器質的疾患への診断および治療が早期に行われることで、Qualityoflifeの改善や疾患の早期発見が期待できる。しかしながら、「女性専用外来」を受診する患者は症状が多岐に及んでおり、ある程度経験を積んだ医師が、時間をかけて行わなければ、なかなかうまくいかないようである。最も重要なのは患者の満足を高めるような外来にしなければいけないことである。白衣を見るとうまく話せなく人もいるので、可能ならば、医師も白衣を脱いで患者と同じ視線で接することが重要である。さらに、一般の待合室から離れた診察にするなどプライバシーに注意を払う必要もある。したがって、このような専門外来を開設する際には、残念ながら病院側の負担が多少大きくなる欠点がある。近年、「男性更年期」の存在も指摘されており、中高年以降の社会的な過剰なストレスがうつ病の状況をさらに悪化させているのかもしれない。これからの性差医療では、男性に対する治療も考慮する必要がある。現在の所、「男性専用外来」は全国でも1,2箇所しか開設されていないようである。男性にも女性同様、なかなか日ごろ話しにくいことが多いわけであり、このような専用外来には遠くから通院されている患者も多いように聞いている。今後、日本全国に「女性専用外来」のみならず「男性専用外来」も広がるこ3とを期待する。現代の医療は、寿命の延長のみならず、健康寿命の延長と社会的な役割を考慮したQualityoflifeを高めるような医療が必要とされ始めている。
“男性と女性の違い“、これは、Y染色体の存在によって決定される。Y染色体の大きさはX染色体の半分以下である。しかも、近年のヒト遺伝子の研究によって、Y染色体に存在する遺伝子は10個程しかなく、大部分はJunkDNA(くずDNA)ではないか、と推測されている。性別を作り出している、Y染色体の役割は、いまだ詳細にはわかっておらず、今後の研究が望まれているところである。
平均寿命がどんどん伸びてきて疾患が変化している。明治以前は男女とも平均寿命は40-50歳くらいであった。乳幼児の死亡率が高かったことも理由のひとつであると思うが、高齢者も少なかったのである。しかし、現在のように高齢化社会になり人々がqualityoflife(生活の質)を意識するようになると、ただ長生きするだけでなく、もっといい生活、もっと楽な生活を求めるようになる。現実は、社会環境や文化的環境が男女の健康に及ぼす影響は大きいと思われる。近年、evidencedbasedmedicine(EBM)に則った医療が叫ばれている反面、個々人に応じたテーラーメード医療も重要であると言われている。個人のqualityoflifeを上昇させるよう医療は、まさにテーラーメード医療の一つであると思われる。“男はこうあらねばならない”あるいは“女はこうあらねばならない”というような育った環境が違うなら、精神的に与える影響は異なり、結果も異なる可能性がある。勿論、男性と女性では性染色体が異なるため遺伝的には違いがあるわけであるが、この遺伝的要因のみならず、文化、民族、性的役割の違いなどに起因する環境因子の違いにも着目した医療こそがgenderspecificmedicineと考えられる。このような医療を提供していく時代がすぐそこまで迫ってきている。
Copyright © 2014 Japan NAHW Network. All Rights Reserved.